八尾市の内視鏡検査でピロリ菌感染症を診断!胃がんリスクを評価するために

ピロリ菌感染症と胃がんの関連性について
国立がん研究センターの情報によると、胃がんの約99%はピロリ菌(正式名称:ヘリコバクター・ピロリ)の感染が原因であり、感染した胃粘膜の慢性炎症(慢性胃炎)によって発症するとされています。ピロリ菌の感染経路はまだはっきりと解明されてはいませんが、免疫力の弱い乳幼児期に感染するものと考えられています。
ピロリ菌に感染していたとしても、何らかの疾患を発症するのは保菌者の3割程度です。しかし、ピロリ菌感染者は胃がんリスクが約5倍に高まるため、除菌をするのがおすすめです。
内視鏡検査でピロリ菌感染を診断する方法
ピロリ菌の感染を診断するには、大きく2つの方法があります。内視鏡検査と、血液や尿・呼気での検査です。内視鏡を用いる検査方法にもいくつか種類がありますが、広く用いられているのは「迅速ウレアーゼ試験法」です。
ピロリ菌が持つ酵素(ウレアーゼ)が尿素を分解し、アンモニアを作る働きを利用し、アンモニアがあると赤くなる試薬を使って胃の組織のpHを検査します。採取した粘膜を反応液に入れるだけの手軽さで、内視鏡検査後すぐ結果が判明されます。
ピロリ菌感染症の治療方針と予防法
ピロリ菌は、1週間程度の服用で除菌治療が可能です。薬の内容としては、胃酸の分泌を抑制する薬と2種類の抗生剤が用いられ、患者さんによっては胃の粘膜を守る薬も一緒に併用します。この時、約8割程度の人は除菌に成功しますが、除菌後の判定検査で菌が認められた場合、べつの薬を組み合わせての2度目の除菌を行います。
ピロリ菌は乳幼児期に感染し、大人になってからは保菌者とキスなどをしてもうつることはありません。生活インフラが整わない発展途上国などで生活をすると、感染する可能性があるので、飲み水などに注意しましょう。
関連記事
-
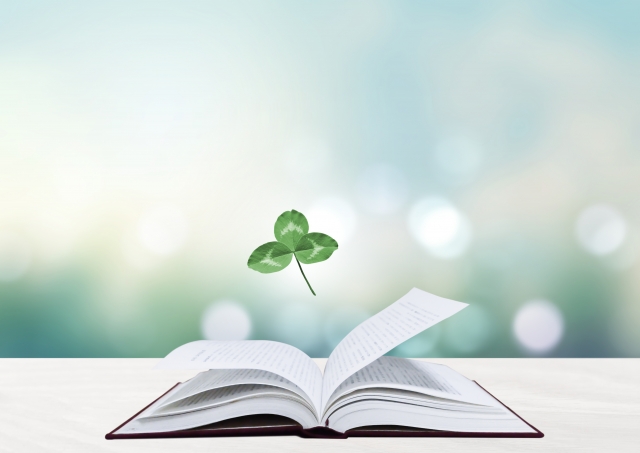 八尾市のがん検診で内視鏡検査を行うことでの早期発見・早期治療の重要性
八尾市のがん検診で内視鏡検査を行うことでの早期発見・早期治療の重要性 -
 八尾市のおすすめの大腸がん検診に内視鏡を取り入れることの意義と効果について
八尾市のおすすめの大腸がん検診に内視鏡を取り入れることの意義と効果について -
 八尾市で逆流性食道炎の内視鏡検査を受ける重要性!効果的な治療と予防方法
八尾市で逆流性食道炎の内視鏡検査を受ける重要性!効果的な治療と予防方法 -
 日帰りで内視鏡検査を受けるメリットと注意点!短時間で気軽に検査を受けられる体制とは
日帰りで内視鏡検査を受けるメリットと注意点!短時間で気軽に検査を受けられる体制とは -
 八尾市で内視鏡検査に使われるおすすめのカメラの種類とは?
八尾市で内視鏡検査に使われるおすすめのカメラの種類とは? -
 八尾市のおすすめ内視鏡クリニックでは充実した問診票で患者さんの状態を把握!適切な検査を実現
八尾市のおすすめ内視鏡クリニックでは充実した問診票で患者さんの状態を把握!適切な検査を実現 -
 八尾市の内視鏡クリニックは学会発表にも積極的!最新知見を取り入れた質の高い医療
八尾市の内視鏡クリニックは学会発表にも積極的!最新知見を取り入れた質の高い医療 -
 八尾市でおすすめの17時以降に内視鏡検査を受けられる意義!仕事帰りでも気軽に検査を受けられる環境
八尾市でおすすめの17時以降に内視鏡検査を受けられる意義!仕事帰りでも気軽に検査を受けられる環境 -
 八尾市の人間ドックで内視鏡検査を受ける意義と注意点!おすすめの総合的な健康チェックの一環として
八尾市の人間ドックで内視鏡検査を受ける意義と注意点!おすすめの総合的な健康チェックの一環として -
 八尾市の内視鏡検査で気をつけたい麻酔の種類と副作用は?
八尾市の内視鏡検査で気をつけたい麻酔の種類と副作用は? -
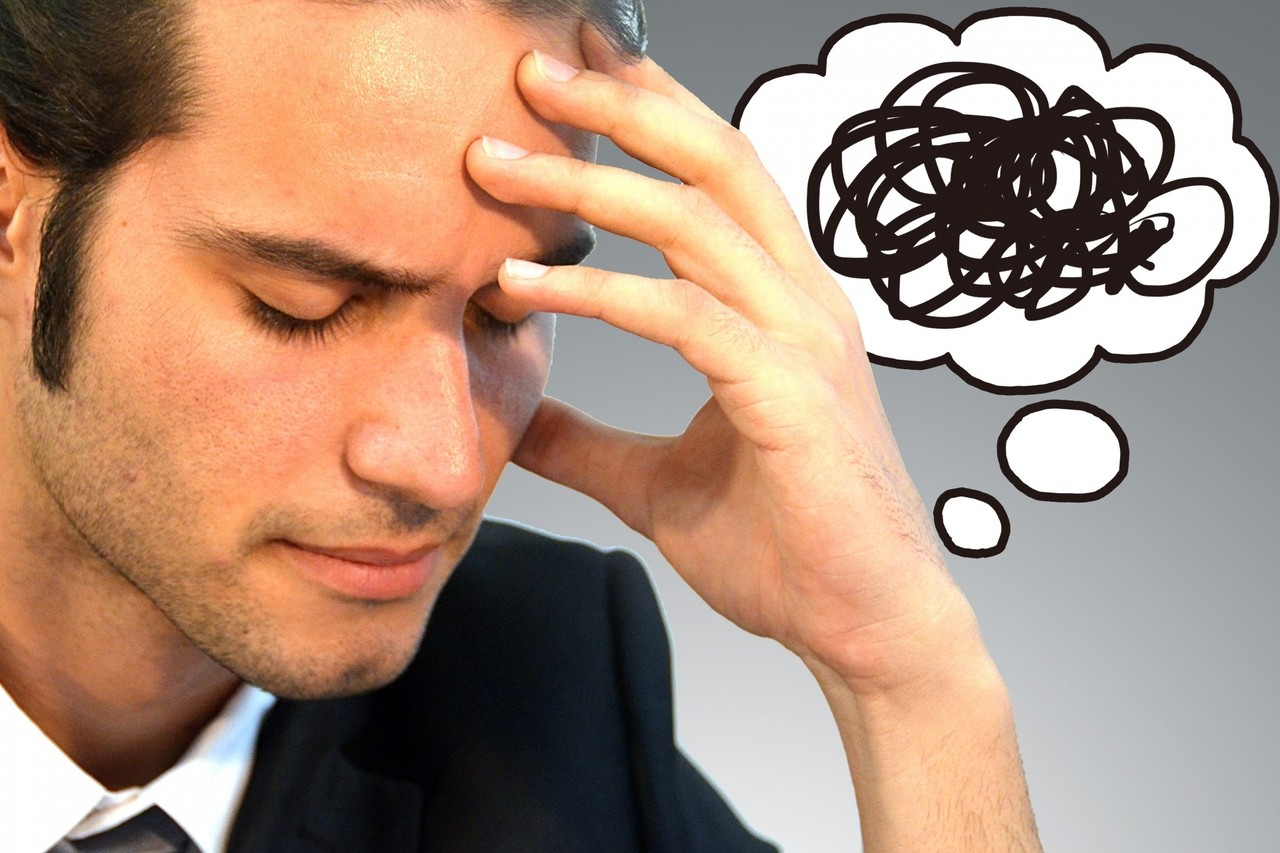 八尾市で内視鏡検査を受けてポリープを早期発見!放置すると大変なことに?
八尾市で内視鏡検査を受けてポリープを早期発見!放置すると大変なことに? -
 八尾市の内視鏡検査が疾病予防に果たす役割とは?早期発見の重要性
八尾市の内視鏡検査が疾病予防に果たす役割とは?早期発見の重要性 -
 八尾市の内視鏡検査で笑顔に!大腸カメラ専用スペースを完備した医療機関とは?
八尾市の内視鏡検査で笑顔に!大腸カメラ専用スペースを完備した医療機関とは? -
 八尾市で血便に悩む人必見!内視鏡検査でおすすめのクリニックの見つけ方
八尾市で血便に悩む人必見!内視鏡検査でおすすめのクリニックの見つけ方 -
 八尾市で内視鏡検査を受けるなら症状に応じてクリニックを選択しよう
八尾市で内視鏡検査を受けるなら症状に応じてクリニックを選択しよう -
 八尾市のERCP検査とは?内視鏡検査の意義と受診する際の注意点
八尾市のERCP検査とは?内視鏡検査の意義と受診する際の注意点 -
 八尾市で内視鏡検査における洗浄消毒の重要性と最新技術!安全な検査を受けるための知識
八尾市で内視鏡検査における洗浄消毒の重要性と最新技術!安全な検査を受けるための知識 -
 八尾市の便秘でお困りの方必見!内視鏡検査で原因を特定しおすすめの治療法を見つけよう
八尾市の便秘でお困りの方必見!内視鏡検査で原因を特定しおすすめの治療法を見つけよう -
 八尾市で大腸がん検診の内視鏡検査を受けるなら?おすすめの時期と準備
八尾市で大腸がん検診の内視鏡検査を受けるなら?おすすめの時期と準備 -
 八尾市で胃がんの早期発見を目指すなら内視鏡検査!信頼できるクリニックを厳選
八尾市で胃がんの早期発見を目指すなら内視鏡検査!信頼できるクリニックを厳選 -
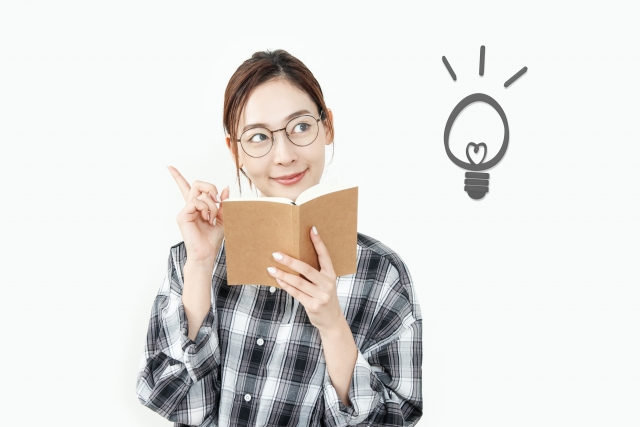 検査前の説明が丁寧なこのクリニックなら安心して検査を受けられる
検査前の説明が丁寧なこのクリニックなら安心して検査を受けられる -
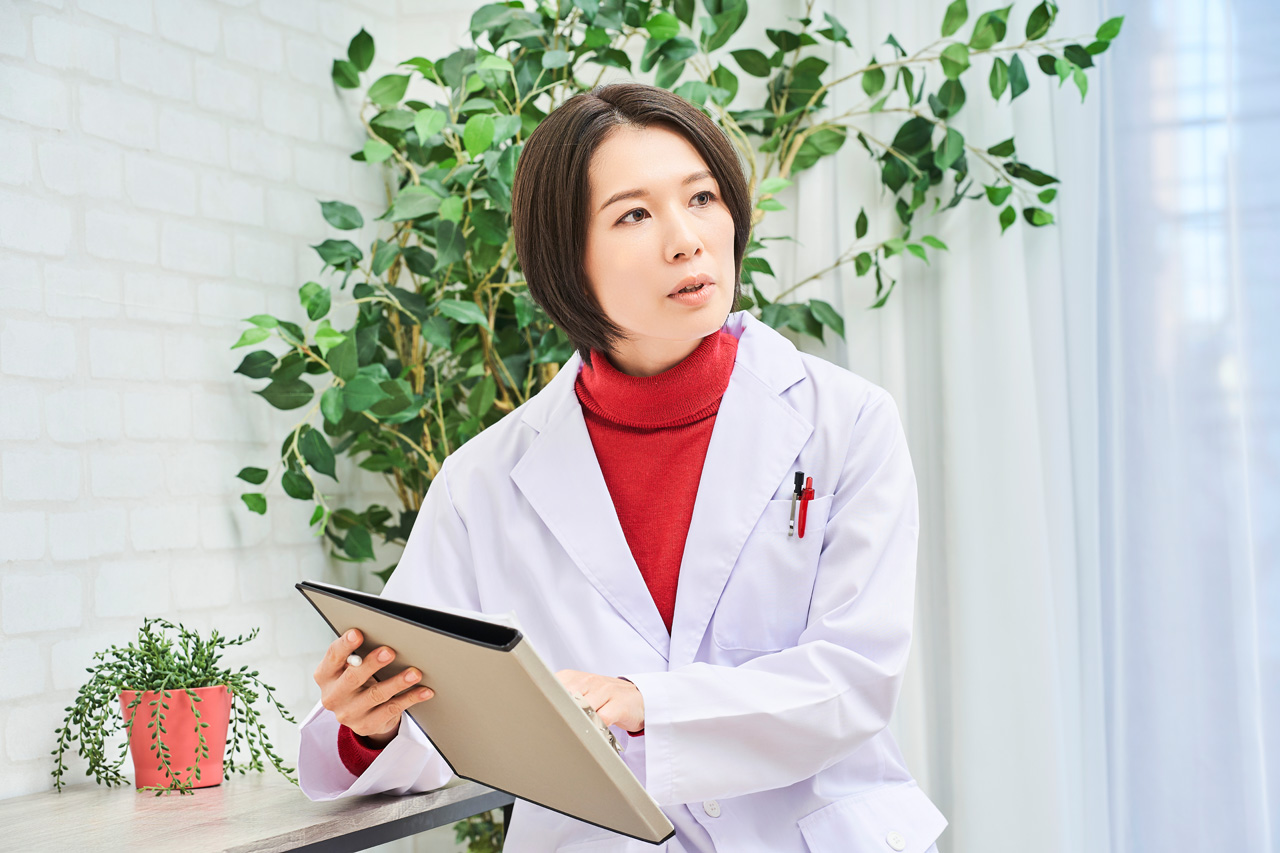 八尾市で経鼻カメラによる内視鏡検査が受けられるおすすめクリニック!楽な検査を体験しよう
八尾市で経鼻カメラによる内視鏡検査が受けられるおすすめクリニック!楽な検査を体験しよう -
 八尾市のおすすめの内視鏡検査の内容や所要時間とは?
八尾市のおすすめの内視鏡検査の内容や所要時間とは? -
 八尾市で内視鏡検査前に知っておきたい!下剤の種類と服用方法
八尾市で内視鏡検査前に知っておきたい!下剤の種類と服用方法 -
 八尾市で内視鏡検査の結果外科手術が必要になったらどうするべきか?
八尾市で内視鏡検査の結果外科手術が必要になったらどうするべきか? -
 八尾市の内視鏡検査でピロリ菌感染症を診断!胃がんリスクを評価するために
八尾市の内視鏡検査でピロリ菌感染症を診断!胃がんリスクを評価するために -
 八尾市でリカバリールームが完備された内視鏡クリニックなら検査後も快適に過ごせる
八尾市でリカバリールームが完備された内視鏡クリニックなら検査後も快適に過ごせる -
 八尾市で内視鏡検査を受ける際に便利な駐車場を備えたおすすめ病院は?スムーズな通院をサポート
八尾市で内視鏡検査を受ける際に便利な駐車場を備えたおすすめ病院は?スムーズな通院をサポート -
 八尾市で内視鏡検査を受けるなら消化器内視鏡専門医がいるクリニックがおすすめ!
八尾市で内視鏡検査を受けるなら消化器内視鏡専門医がいるクリニックがおすすめ! -
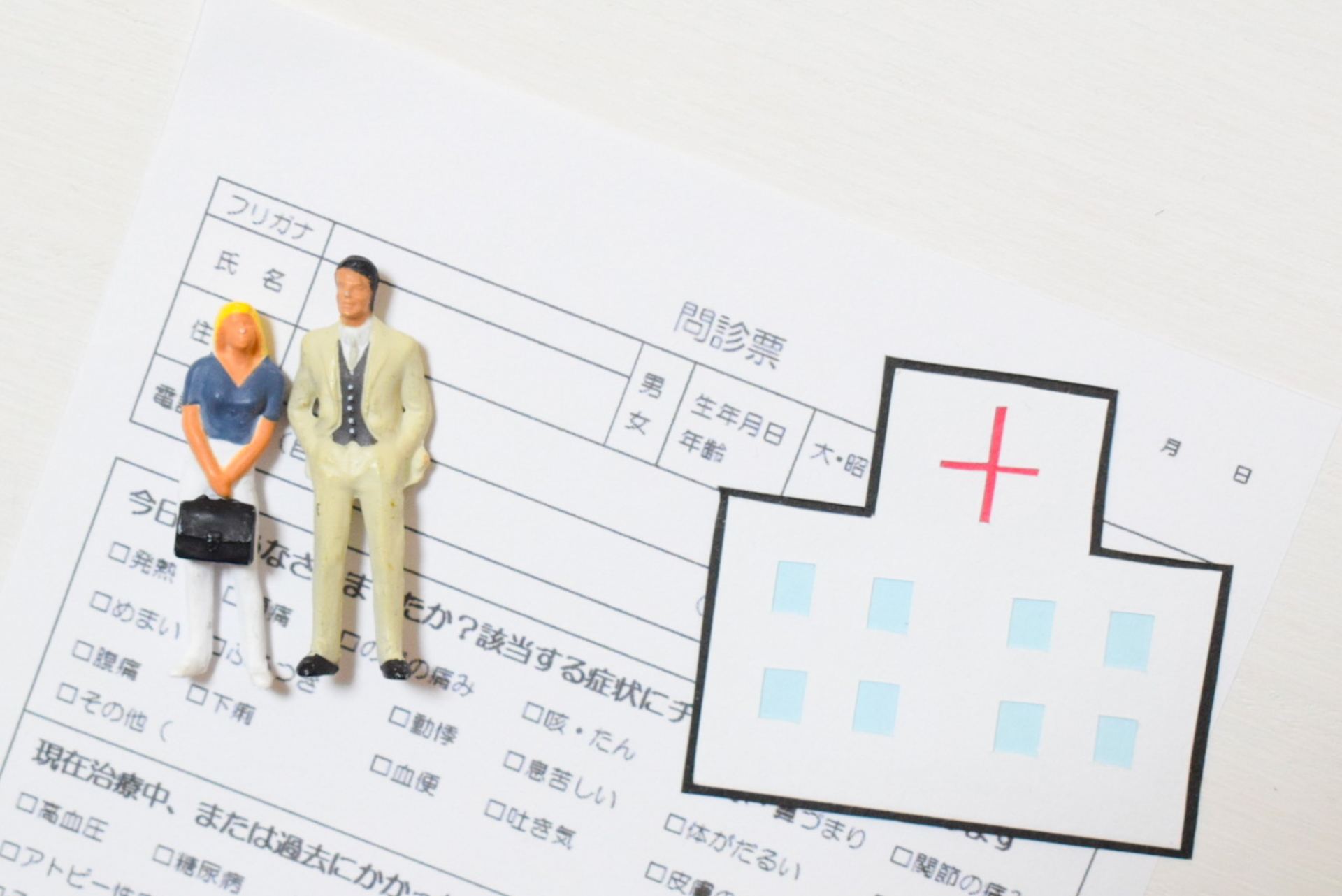 八尾市で糖尿病患者さんにおすすめの内視鏡検査クリニック!合併症リスクに配慮した検査を
八尾市で糖尿病患者さんにおすすめの内視鏡検査クリニック!合併症リスクに配慮した検査を -
 八尾市で土曜日に内視鏡検査が受けられるメリットとは
八尾市で土曜日に内視鏡検査が受けられるメリットとは -
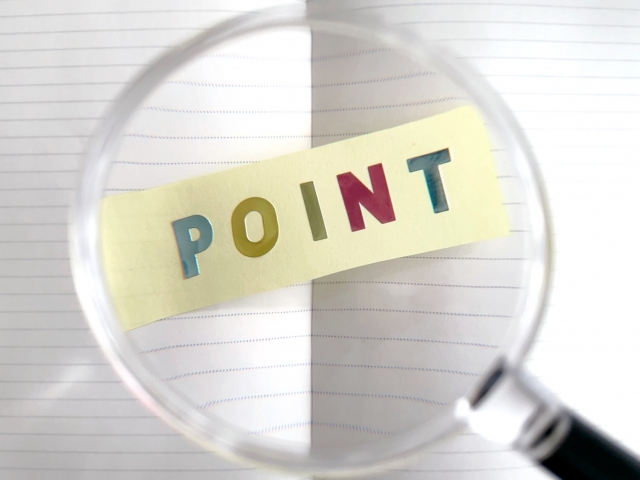 八尾市で内視鏡検査のリスクとその対策!安全に検査を受けるためのポイント
八尾市で内視鏡検査のリスクとその対策!安全に検査を受けるためのポイント -
 八尾市の内視鏡検査なら信頼できる評判の医療機関を選ぼう!
八尾市の内視鏡検査なら信頼できる評判の医療機関を選ぼう!